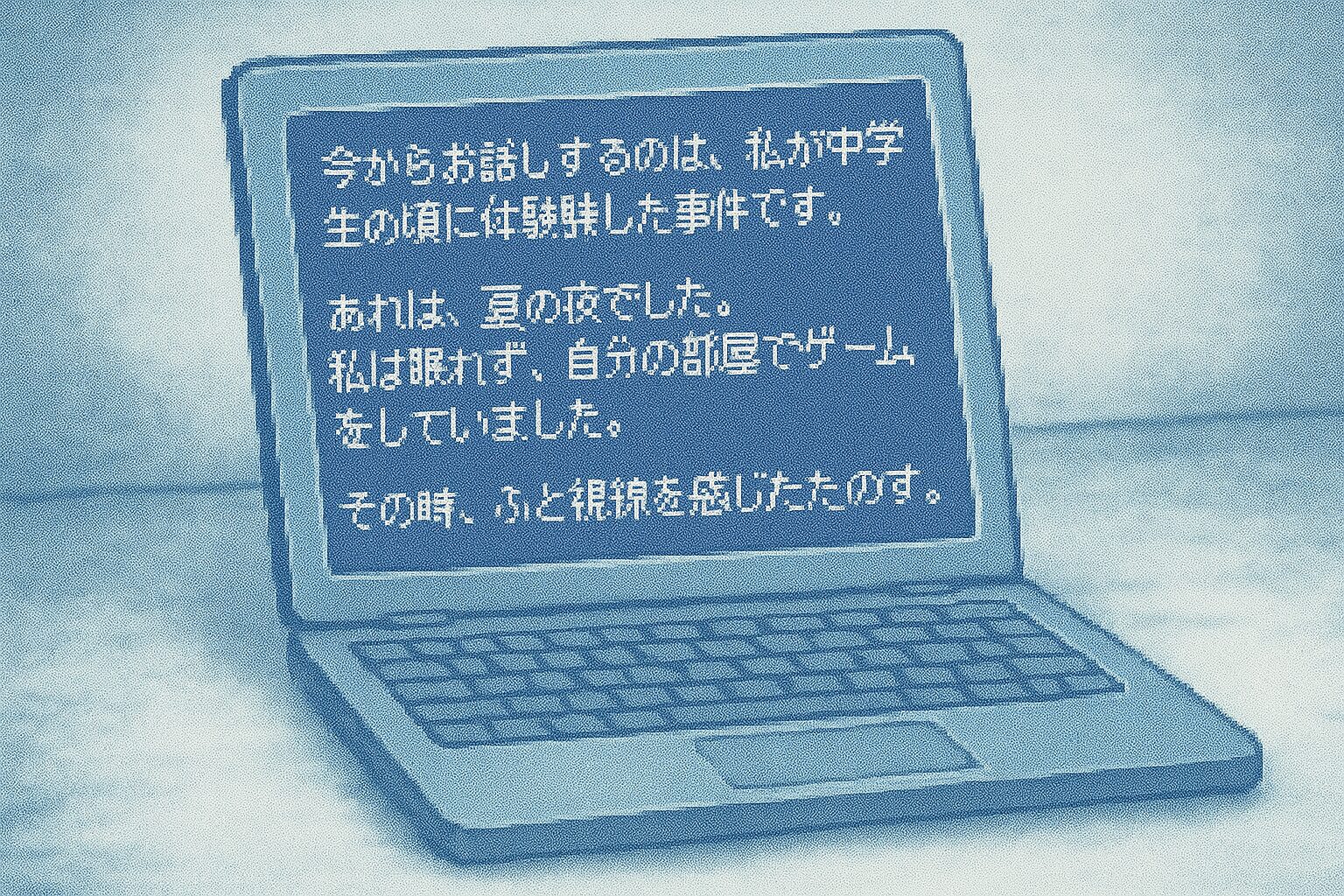山田は新しい小説の執筆に没頭していた。「血の色をした夕焼け」というタイトルのミステリー小説だ。彼は昨年、同人誌でひそかに人気を博し、ついに商業デビューが決まったばかりだった。
「よし、今日も3000字は書けたな」
彼はクラウド保存機能付きのワープロソフトを使っていた。このソフトは5分ごとにオート保存される優れものだ。データを失うリスクが少なく、彼のような心配性にはぴったりだった。
「今日はここまでにしておこう」
彼はパソコンを閉じ、ベッドに向かった。充実感とともに、明日も書き進められることへの期待で胸が膨らんでいた。
翌朝、彼はいつものようにパソコンを開き、作業を再開した。ファイルを開くと、ひとつ気になることがあった。
「あれ?」
文末に見覚えのない一文が追加されていた。
『彼は知らなかった。これが最後の夜明けになるとは。』
山田は首をかしげた。確かに昨晩は疲れていたが、そんな文章を書いた覚えはない。しかし小説の展開としては悪くないアイデアだ。彼は肩をすくめると、そのまま執筆を続けた。
次の日も同じことが起きた。彼が書いていない謎の一文が追加されていた。
『壁の時計が止まったとき、彼の時間も止まる。』
さすがに不気味に感じた山田は、クラウドの保存履歴を確認した。最後の保存は昨夜の23時55分。彼がパソコンをシャットダウンした直後だ。恐る恐る書き込み時間を確認すると、その不可解な一文は0時5分に追加されていた。
「誰かがアカウントにハッキングしたのか?」
パスワードを変更し、二段階認証を設定した山田は、不安を払拭するように執筆を続けた。
三日目。彼は警戒心を持ってファイルを開いた。案の定、新しい文章が追加されていた。
『彼の胸に走る痛み。左腕がしびれ、冷や汗が背中を伝う。それは前触れだった。』
文章のスタイルが山田自身のものと非常に似ていることに気づいた。これは単なるいたずらなのか、それとも…。彼は震える手でログイン履歴を確認したが、不審なアクセスは見当たらなかった。
四日目。すでに予想していたように、新たな文章が追加されていた。
『呼吸が苦しくなり、床に倒れる。誰も助けに来ない。携帯は手の届かない場所に。』
恐怖が山田の背筋を走った。これはもはや脅迫ではないのか。彼は警察に相談することも考えたが、何と説明すればいいのだろう。「私が書いていない文章が勝手に追加されています」と言えば、精神科を勧められるだけだろう。
五日目。今度はより具体的な記述だった。
『4月8日、午後11時23分。山田の部屋で、彼は一人、心臓発作で命を落とす。原稿は未完のまま、パソコンの画面だけが青白く光る。』
明日は4月8日。山田の手は震えが止まらなかった。これは冗談ではない。彼は友人の家に泊まることにし、翌日の午後11時には絶対に一人にならないよう手配した。
4月8日、午後10時。友人の家でテレビを見ながら、山田はやっと安堵していた。「何も起きない」と自分に言い聞かせた。
そのとき、友人が突然「ああ、忘れてた!コンビニでタバコ買ってくる!」と言い出した。
「待って!今行かないでくれ!」
山田は必死に引き留めたが、友人は「すぐ戻る」と約束し、出て行った。
部屋に一人残された山田は、時計を見た。午後11時15分。あと8分。
彼は緊張のあまり息が苦しくなってきた。胸が締め付けられるような感覚。
「気のせいだ…気のせいだ…」
スマホを手に取り、救急車を呼ぼうとしたが、画面が突然フリーズした。
午後11時20分。左腕がしびれてきた。冷や汗が背中を伝う。
「これは…心臓発作の症状じゃないか…」
彼は床に倒れ、携帯をテーブルの上に落とした。手が届かない。
午後11時22分。呼吸が苦しくなってきた。山田は、自分の小説の登場人物のように、これが「最後の夜明け」なのだと悟った。
午後11時23分。友人が部屋に戻ってきたとき、山田はすでに冷たくなっていた。
数日後、警察は捜査の一環として彼のパソコンを調べた。クラウド上に保存された小説ファイルには、山田の死の瞬間まで克明に記録されていた。そして最後の文章は、死亡時刻の1分後に保存されていた。
『これで物語は完成した。次は、あなたの番だ。』
その日から、山田の小説「血の色をした夕焼け」は、インターネット上で奇妙な人気を博していった。読者は皆、その臨場感あふれるリアルな死の描写に魅了されていた。
そして、その小説を最後まで読んだ人々の中から、同じような不可解な追記現象が報告され始めた…。